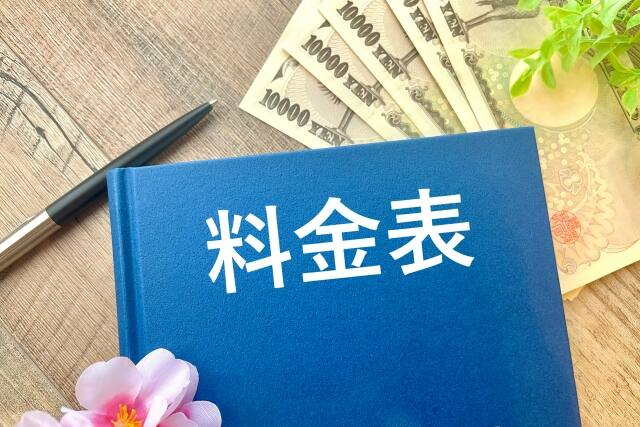ビザ・在留手続きで不許可・不交付になった場合(Not allowed Not issued)

更新や変更が不許可の場合は、在留期限が1カ月を切っているような場合を除いて、有効期限まで在留することはできます。
もし、不許可になった場合は、在留資格の有効期限までに改めて在留資格変更許可申請を行うか、現状の在留資格に該当する活動に戻るか、帰国するかの選択を迫られます。
不許可の処分通知
ビザ・在留手続きの処分の通知がされます。
申請人(外国人本人)の出頭が求められます。
不許可の処分の通知が渡されるか、事前に郵送されます。
中長期在留者から在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請に対して不許可とする場合
申請人(外国人本人)の出頭を求められます。
出頭を求められた際に在留カードの裏面にある「申請中」であることが二重線で取り消されます。
不許可の通知を直ちに行う場合
口頭または電話で申請人(外国人本人)対して通知されます。
特例期間内に不許可処分になった場合
在留資格変更許可又は在留期間の更新許可の申請を在留期間満了日を超えた特例期間内に不許可処分になった場合は以下の通りです。
出国準備期間の付与
「今回の申請内容では許可できない旨」の告知がされます。
そして、入管は申請人(外国人本人)に対し、今回の申請の内容を「出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」に変更する意思の有無について確認してきます。
申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望する場合
「申請内容変更申出書」を提出します。
そして、特段の事情がないときは、30日以下の在留期間が付与されます。
特例期間が設けられないように30日以下の在留期間になってしまうようです。
申請人が在留資格「特定活動の出国準備を目的とする在留資格の変更許可申請」への変更を希望しない場合
変更する意思を有さないとして「申請内容変更申出書」を提出しない者については、不許可処分になります。
そして不許可通知書を交付して、不許可とする旨を告知し、誓備部門に引き渡されます。
不許可処分になった場合の対策
不許可処分になった場合は、先ほどに申し上げた通り、いずれかの選択が必要です。
- 在留資格の有効期限までに改めて在留資格変更許可申請を行う
- 現状の在留資格に該当する活動に戻る
- 帰国する
もし再申請をする場合、入管の審査場の誤りや事実誤認があった場合は、それらを丁寧に説明して再申請することがあげられます。
不許可の通知になった場合は、審査を担当した入管に「不許可の理由」を聞きに行くのが対策になります。
再申請する場合、不許可になった理由を担当した審査官から聞いて、その問題点を払拭(リカバリー)できるかどうかが成功するカギになります。
もし、問題点を払拭せず(リカバリー)せず再申請したところで結果は変わりません。
不許可になった理由が、たとえば「過去の在留状況が良くなかった」、つまり不許可の理由が(相当性)の場合は、「過去の在留状況が良くなかった(相当性)」に関して入管の事実誤認であった場合を除いて、経験上、再申請をしたとしても不許可の理由を払拭することはきわめて難しいです。
不許可の理由が「相当性」の場合は、いったん帰国して、在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うことが対策になります。
というのは、在留資格認定証明書交付申請において、過去の在留状況が良くなかった(相当性)は入管の審査対象とはならないからなのです。