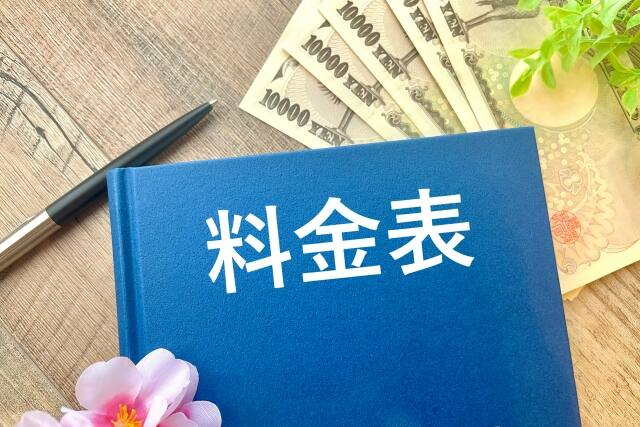在留資格「高度専門職1号」 (highly-skilled-professionals1)

「高度専門職1号」ビザとは
「高度専門職」ビザを持った在留する外国人の人数
| 2022年12月末 | 2023年12月末 | 2024年12月末 | |
|---|---|---|---|
| 高度専門職1号(イ) | 2,030人 | 2,281人 | 2,528人 |
| 高度専門職1号(ロ) | 13,972人 | 17,978人 | 21,094人 |
| 高度専門職1号(ハ) | 1,116人 | 2,219人 | 3,338人 |
| 高度専門職2号 | 1,197人 | 1,480人 | 1,748人 |
| 合計人数 | 18,315人 | 23,958人 | 28,708人 |
「高度専門職1号」ビザとは、高度の専門的な能力を有する外国人材の受け入れを促進するために、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格になります。
学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に「高度専門職1号」の在留資格が許可されます。
「高度専門職1号」ビザのは、「ポイント制度がなくても、入国し、在留することができる外国人、すなわち「在留資格」がある外国人についてポイントが高ければ、一定の優遇措置の対象にします」という制度なのです。
また「高度専門職」ビザは、永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されており、いわゆる「日本版高度外国人材グリーンカード」とも言われています。
「高度専門職1号」ビザは、区分在留資格ともいわれており、活動内容により(イ)、(ロ)、(ハ)の3つに分かれています。
- 高度学術研究活動をする「高度専門職1号(イ)」
- 高度専門・技術活動をする「高度専門職1号(ロ)」
- 高度経営・管理活動をする「高度専門職1号(ハ)」
さらにそれぞれの活動の特性に応じ
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 研究実績
などの項目ごとにポイントを設け、外国人の方が希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を目的としています。
「高度専門職」の在留資格は、ポイントが高い人材、すなわち高度な知識や技術を持っている外国人に対して在留資格を付与するものではなく、日本において高度な知識や技術を必要とする業務の活動をする場合に付与される在留資格です。
高度専門職ビザの在留期間は
- 高度専門職1号の在留期間は5年
- 高度専門職2号の在留期間は無期限
になります。
「高度専門職」ビザのメリット
「高度専門職」ビザがある外国人は、高度な専門的能力を有し、日本に対して学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれますので、優秀な外国人の受入を一層促進するために、様々な出入国在留管理上の優遇措置が設けられています。
「高度専門職」ビザには出入国在留管理上の優遇措置として、次のようなメリットがあります。
「高度専門職1号」ビザのメリット
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
| メリット | メリットの詳細 |
|---|---|
| 永住許可要件の大幅緩和 | 「その者の永住が日本国の利益に合する」として、日本における在留歴に関する要件について特例があります。 |
| 関係者にかかわる優遇 |
配偶者が就労できます(一定の要件の下) |
| 入国・在留申請の優先処理 | 他のビザと別枠なので、出入国在留管理局で優先される対応を受けることができます |
| 高度専門職1号の在留期間は一律5年 | いきなりビザの最長期間である5年のビザがもらえます |
| 複数の活動ができる | 1つのビザには1つの活動が定められていますが、このビザは複数の活動ができるビザになります。 |
在留歴に係る永住許可要件の緩和とは
「高度専門職1号」ビザのメリットとして在留歴に係る永住許可要件の緩和があげられます。
在留歴に係る永住許可要件の緩和とは、永住許可を取得するためには、通常、日本での在留年数が原則10年以上必要ですが、特例として10年以上在留していなくても、永住許可の対象となります。
たとえば、次のような場合は永住許可要件の緩和の対象になります。
- 高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合
- 高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- (ア)「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
- (イ)3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- (ア)「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
- (イ)1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
- (ア)「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
- (イ)1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
「高度専門職」ビザを持つ高度外国人材の具体例
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイントの合計が70点以上に達した者が高度外国人材と言われます。
「高度専門職」ビザのポイント計算の例(経営支援ソフトの開発業務に従事する場合)
| 項目 | 点数 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 30歳 | 10点 |
| 年収 | 600万円 | 20点 |
| 学歴 | 外国の大学卒業で修士号MBAを取得 | 25点 |
| 職歴 | IT関連7年 | 15点 |
| ポイント合計 | 70点 |
などがあげられます。
高度専門職1号の在留資格該当性

「高度専門職1号」ビザに定められた活動に該当することを「在留資格該当性」といいます。
まず「高度専門職1号」ビザを取得するためには、「在留資格該当性」を満たさないとなりません。
「高度専門職1号」ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人の受入の促進のために設けられた在留資格になります。
入管法には「高度専門職1号」ビザの該当性を以下のように定めています。
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
(イ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
(ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
(ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
【入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄】
「高度専門職1号」ビザに該当する活動とは
「高度専門職1号」ビザに該当する活動は、高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う、次のいずれかにあたる活動です。
- 「高度専門職1号(イ)」の高度学術研究活動
- 「高度専門職1号(ロ)」の高度専門・技術活動
- 「高度専門職1号(ハ)」の高度経営・管理活動
「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準」とは
「高度の専門的な能力を有する人材として定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準です。
この省令は、ポイント計算にかかわる基準を定めており、
- 「高度専門職1号(イ)」
- 「高度専門職1号(ロ)」
- 「高度専門職1号(ハ)」
のそれぞれの活動に応じて
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 研究実績
などの項目ごとにポイントを設定し
- そのポイント合計が70点以上であること
- 「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については報酬年額合計が300万円以上
であることを求めています。
ちなみに「高度専門職1号(ロ)」および「高度専門職1号(ハ)」については、ポイント計算して70点以上あったとしても年収が300万円未満の場合は「高度専門職」外国人と認定されませんので注意が必要です。
「高度専門職1号(イ)」とは
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自らの事業を経営する活動または当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動
「高度専門職1号(イ)」
「高度専門職1号(イ)」は、高度学術研究活動が該当します。
具体的には、「教授」、「研究」、「特定活動告示36号」などの在留資格が想定されます。
また教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、宗教、技能そして特定活動告示37号の可能性もあります。
具体的には、
- 大学等の教育機関で教育をする者
- 民間企業の研究所で研究をする者
- 上記の活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営する者
に付与されることを典型として想定している在留資格になります。
「高度専門職1号(イ)」の対象となる主な者
相当程度の研究実績を有する
- 研究者
- 科学者
- 大学教授
などがあげられます。
「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは
「教授」の在留資格に規定する「研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とほぼ同じ意味です。
「高度専門職1号(イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
なお、「教授」、「教育」の在留資格と異なり、活動する場を教育機関に限定していないため、例えば民間企業の社内研修で教育をする活動も該当します。
「(当該活動と併せて)当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動」とは
主たる活動に係る契約機関以外の機関との契約に基づく活動を許容するという内容です。
ただし、「当該活動と併せて」と規定しているため、主たる活動に係る契約機関との契約に基づく活動を行っていない場合は、それ以外の機関との契約に基づく活動を行うことはできません。
「高度専門職1号(ロ)」とは
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動
「高度専門職1号(ロ)」
「高度専門職1号(ロ)」は、高度専門・技術活動が該当します。
具体的には、「法律・会計業務」、「医療」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」そして「特定活動告示37号」の在留資格が想定されます。
また、教授、芸術、報道、経営・管理、研究、教育、介護、興行そして特定活動告示36号の可能性もあります。
具体例は
- 医師
- 弁護士
- 情報通信分野等の高度な専門資格を有する技術者
- 上記の活動と関連する事業を起こし自ら経営する者
が専門的な就労活動に従事する場合に付与されることを典型として想定している在留資格になります。
「高度専門職1号(ロ)」の対象となる主な者は
医師、弁護士、情報通信分野などの高度な専門資格を有する者が主な対象者になります。
「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とは
「技術・人文知識・国際業務」ビザの規定にある「自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動」とほぼ同じ意味です。
ただし、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格においては、「技術・人文知識•国際業務ビザ」の在留資格に相当する活動のうち「国際業務」の部分は含まれません。
なぜなら、「国際業務」は 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」であり、「高度専門職1号(ロ)」の在留資格の概念には適しないとともに、思考や感受性のレベルの高低をポイントで計算することが難しいからです。
「高度専門職1号(ハ)」とは
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動
「高度専門職1号(ハ)」
「高度専門職1号(ハ)」とは、高度経営・管理活動が該当します。
具体的には、「経営・管理」または「法律・会計業務」の在留資格が想定されます。
また、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「芸術」、「報道」、「医療」、「研究」、「特定活動告示36号」または「特定活動告示37号」の可能性があります。
具体例は
- 相当規模の企業の経営者
- 管理者等の上級幹部
- 上記の活動と併せて、これらの会社や事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営する者
が当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与されることを典型として想定している在留資格です。
「高度専門職1号(ハ)」の対象となる主な者は
相当程度の企業の経営者および管理者などの上級幹部が主な対象者になります。
「高度専門職1号(ハ)」の在留資格においては、「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」も行うことができるようにりました。
「当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」とは
主たる活動の研究の成果や知識・技術を生かしてベンチャー企業を経営する等の活動を想定しています。
ただし、「当該活動と併せて」と規定しているので、主たる活動を行わず、それらの付帯的な活動のみ行うことは認められません。
また、主たる活動として指定された会社の役員として活動している者が、
- 同種同業の他社の社外取締役を兼任したり
- 特定された会社以外に子会社を設立して経営する
といった活動を想定しています。
主たる経営活動との関連性が必要であるので、例えば IT企業の役員が飲食業を経営するのは対象外となります。
高度専門職1号の要件(上陸許可基準適合性)

上陸許可基準適合性とは、在留資格該当性があると考えられる外国人が、ビザ申請の際に、満たしていなければならない要件(基準)であり、基準に適合しているかどうかを意味します。
審査基準(上陸許可基準適合性)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第1条第1項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
(第1号)
次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第1の1の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
口 本邦において行おうとする活動が法別表第1の2の表の「経営・管理」の項から「技能」の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
(第2号)
本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合でないこと。【上陸基準省令の「高度専門職1号」の項の下欄】
「高度専門職1号」ビザの要件とは
「高度専門職1号」上陸許可基準に適合するとは、高度専門職省令第1条第1項に掲げる基準に適合することに加えて、
- (第1号)「次のいずれかに該当すること」
- (第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」
のいずれにも適合することが必要です。
(第1号)「次のいずれかに該当すること」とは
「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得できる外国人にかかわる要件について定めたものになります。
「高度専門職1号」ビザの在留資格を取得しようとする外国人は
のいずれかの在留資格(ビザ)があることが必要です。
(第2号)「本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影密等の観点から相当でないと認める場合」とは
高度専門職1号の在留資格を申請する外国人が日本において行おうとする活動が、産業及び日本人の生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合には、「高度専門職1号」の基準に適合しないとなります。
次のような観点から「高度専門職」の在留資格を付与することが相当でないかどうか判断されます。
- 産業界や日本人の就職、労働条件などに及ぼす影響の有無や程度
- 教育関係への影響
- 公共の安全確保に与える影響
- 対外関係への配慮
- 治安、社会秩序に与える影懇
よくある質問Q&A
Q 大学を卒業しました。翻訳・通訳をする「国際業務」として「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っています。「高度専門職1号」ビザへ変更できますか?
「高度専門職1号」ビザへ変更できない可能性が高いです。
「国際業務」は、「高度専門職1号(ロ)」の対象から除外されているためです。
もし、あなたが、大学にて日本語を専攻していた場合は、「人文知識」として「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しますので、「高度専門職1号」へ変更ができます。
Q 「高度専門職」ビザの要件にある本邦の公私の機関との契約とは?
本邦の公私の機関との契約とは、雇用契約が一般的ですが、他にも、継続的に見込まれるのであれば、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
特定の機関(複数でもOK)との継続的なものでなければなりません。
ちなみに、本邦の公私の機関には、法人だけでなく、個人事業主でも問題ありません。
Q ポイント計算を行う時点は、どの時点を基準にするのでしょうか?
ポイント計算を行う時点は、次の時点になります。
- 上陸許可を受けるとき
- 上陸特別許可を受けるとき
- 在留資格変更許可を受けるとき
- 在留期間更新許可を受けるとき
- 在留資格取得許可を受けるとき
- 在留特別許可を受けるとき
実際には、上記の許可に係る申請や裁決の時点を基準にポイント計算をします。
「高度専門職1号」ビザを申請するために必要な書類は高度専門職1号の必要書類に記載しています。